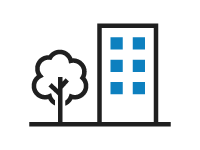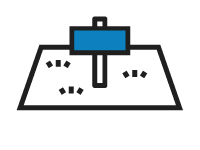生命保険診断

節税対策として生命保険を活用する際は、いくつかのポイントを押さえる必要があります。生命保険を「診断」するというよりも、税制上のメリットを活かして、どのように生命保険を設計し見直すかという視点で考えます。
生命保険で節税できる仕組み
生命保険は、主に以下の3つのタイミングで税制上の優遇措置を受けることができます。
その1:保険料を支払うとき(所得税・住民税の控除)
支払った保険料に応じて生命保険料控除が適用されます。これにより、その年の所得から一定額が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
その2:保険金を受け取るとき(相続税・贈与税の非課税枠)
死亡保険金を受け取る際に、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。この非課税枠「500万円 × 法定相続人の数」が適用されるのは、保険料を被相続人自身が負担していた生命保険金であり、かつ法定相続人が受け取った場合に限られます。例えば相続人が3人いる場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までは、相続税がかかりません。
その3:相続財産として活用するとき(遺産分割対策)
生命保険の保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。特定の相続人に確実に財産を遺したい場合、生命保険を活用することで、遺言書と同じような効果を得ることができます。
また、現金で受け取るため、相続税の納税資金を確保する目的でも有効です。
節税対策のための生命保険診断ポイント
節税を目的とした生命保険の見直しでは、以下の点をチェックすることが重要です。
その1:誰を契約者、被保険者、受取人にするか
保険料を支払う人(契約者)と、保険の対象者(被保険者)、そして保険金を受け取る人(受取人)の関係性によって、かかる税金の種類が変わります
その2:非課税枠を最大限に活用できているか
死亡保険金額が法定相続人の非課税枠を超えていないか、また、その非課税枠を有効に活用できているかを確認します。
その3:他の相続財産とのバランス
不動産など流動性の低い財産が多い場合、生命保険の現金を受け取ることで、納税資金や遺産分割の際の代償金として活用できます。
その4:保障内容の最適化
過剰な保障になっていないか、将来のライフプラン(子どもの教育費、老後の生活費など)と照らし合わせて見直します。
生命保険は、所得税・住民税の節税、相続税の軽減、そして円滑な遺産分割など、様々な面で有効な節税対策となります。節税目的で生命保険を見直す際は、これらのポイントを踏まえた上で、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。