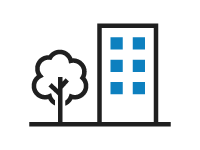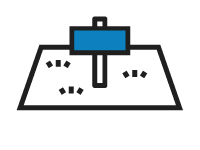相続税の申告は、期限や提出先、必要書類などが定められており、手続きは複雑になることがあります。以下に、その主なポイントをまとめました。
その1:申告の期限と場所
● 期限
相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。

● 提出先
亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地ではないので注意が必要です

その2:申告の流れ
① 相続人の確定
● 遺言書の有無の確認
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるのかを確定します。

▼
② 遺産と債務の把握・相続放棄するか判断と申し立て
● 相続した財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)をすべて把握します。
● 相続放棄をする場合は、相続放棄申述書に必要書類を添えて亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。(期限:3ヶ月)

▼
③ 遺残分割協議・相続税の計算
● 財産の評価額を基に、各種控除や特例を適用して相続税額を計算します。
● 相続人全員で、遺産分割の方法について話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。

▼
④ 相続税の申告・納税
申告書を提出し、税金を納めます。(期限:10ヶ月)

その3:申告書の提出方法
提出方法は以下の3つがあります。
- 税務署の窓口へ持参
- 郵送
- e-Taxによる電子申告

その4:必要な主な書類
申告には、主に以下のような書類が必要です。
● 相続人全員のマイナンバー関係書類
● 相続人全員の身元確認書類のコピー
● 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
● 相続人全員の戸籍謄本
● 遺言書の写し、または遺産分割協議書の原本
● 相続人全員の印鑑証明書
● 財産に関する書類(預金残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書など)
● 債務や葬儀費用に関する領収書
その5:注意点
● 申告・納税の遅れ
申告や納税が遅れると、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
● 専門家への相談
相続税の申告手続きや財産の評価には専門的な知識が必要なため、税理士に依頼するケースが多いです。ストーンズが提携している税理士事務所に相談することも可能です。
● 特例の適用
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、適用することで税額が大幅に減額される特例があります。これらの特例を適用するには、遺産分割協議を終えていることや、申告書に特定の書類を添付することが必要です。
相続税申告の手続きは複雑で多岐にわたるため、ご自身だけで進めるのが難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。