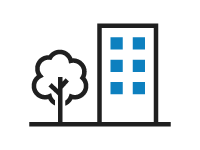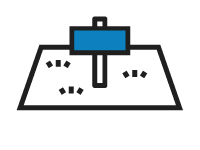財産を受け継ぐ方
相続トラブルの原因
相続トラブルの原因は、お金持ちの家庭だけでなく、どんな家庭でも起こり得ます。主な原因は以下の通りです。
1.遺産が分けにくい
主な財産が自宅の土地や建物といった不動産の場合、物理的に分けることが困難です。売却して現金で分ける、特定の相続人が不動産を取得して他の相続人に代償金を払うなどの方法がありますが、いずれも全員の合意が必要です。
この話し合いがまとまらないと、争いに発展します。
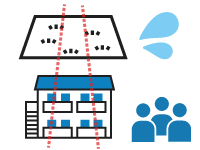
2. 生前の家族関係や貢献度の差
親の介護を献身的に行っていた相続人が、「自分だけ苦労したのに、なぜ財産は均等に分けるのか」と不満を持つことは少なくありません。
また、生前に特定の相続人が多額の援助を受けていた場合、他の相続人がそれを問題視することもあります。

3. 財産の内容が不明瞭
被相続人と同居していた相続人が財産を管理していた場合、他の相続人から「財産を隠しているのでは?」「使い込みがあったのでは?」と疑念を抱かれ、トラブルになることがあります。
また、生前に特定の相続人が多額の援助を受けていた場合、他の相続人がそれを問題視することもあります。
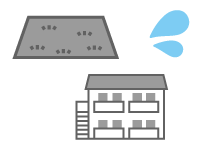
これらの問題は、生前に話し合いをしておくことで回避できる可能性があります。
遺産の配分について
遺産相続の対象・順位・相続割合は民法できまっています。
相続人になれるのは、配偶者・子どもや孫(直系卑属)・両親や祖父母(直系尊属)・兄弟姉妹 などの親族です。
ただし、これらの方全員が遺産を相続できるわけではなく、優先順位(相続順位)が決められています。
相続順位には 第1順位から第3順位まで あり、上位の順位に該当する方がいれば、下位の方は相続人にはなりません。
亡くなられた方の配偶者は、必ず相続人になります。内縁関係にある場合には、この対象となりません。

偏った遺言がある
偏った内容の遺言書があった場合、以下の3つのリスクが考えられます。
1. 相続人間の深刻な対立とトラブル
遺言によって特定の相続人が多くの財産を受け取る一方、他の相続人がほとんど受け取れないような場合、不公平感から激しい感情的な対立が生じやすくなります。遺言書の内容をめぐって家族や親族の関係が悪化し、話し合いでの解決が困難になり、最終的には遺産分割調停や訴訟に発展するリスクが高まります。

2. 遺留分侵害額請求
兄弟姉妹およびその子(代襲相続人)以外の法定相続人には、「遺留分」という法律で保障された最低限の相続分があります。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は、財産を多く受け取った相続人に対して、侵害された分の金銭を請求できます。
この「遺留分侵害額請求」が行われると、請求された側は多額の支払いを求められる可能性があり、大きな負担となります。

3. 遺言の無効・法的な争い
遺言書に形式上の不備があったり、被相続人が認知症などで判断能力が不十分なときに作成されていたりすると、その遺言自体が無効と判断される可能性があります。遺言が無効になった場合、遺言書がない状態での遺産分割協議が必要となり、相続人全員の合意がなければ手続きを進められず、紛争が長期化するリスクがあります。
これらのリスクを避けるためには、遺言書を作成する際に専門家(弁護士や税理士)に相談し、法的に有効かつ公平な内容にすることが重要です。
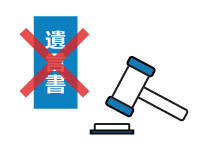
兄弟間で考え方が違う
相続について、兄弟(姉妹)間で意見が違う場合
「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」そう思っていても、不動産が絡む相続では話が別です。「実家は誰が継ぐのか」「売却して現金で分けたい」「自分は貢献してきた分、多く欲しい」など、ご兄弟それぞれの生活状況や想いがあるため、意見がまとまらないケースは少なくありません。さらに、ご兄弟の配偶者の意見が加わり、話が複雑化することも。
分割が難しい不動産は、法律で定められた持分(法定相続分)通りに分けることが難しく、結果的に「争族」となり、家庭裁判所の調停に至ることも増えています。
大切なご家族が円満に相続を終えるために、ご両親が元気なうちに「遺言書」を作成しておくことが最も有効な対策です。私達は、皆様のお気持ちに寄り添い、円満な相続の実現をサポートいたします。

相続に必要な手続き
相続発生後の手続きと流れ
大切な方を亡くされた悲しみの中、相続手続きを進めるのは精神的にも大きな負担です。「何から手をつければ良いのか」「誰に相談すれば良いのか」と、戸惑う方も少なくありません。相続手続きは一般的に以下の流れで進み、多くに期限が設けられています。